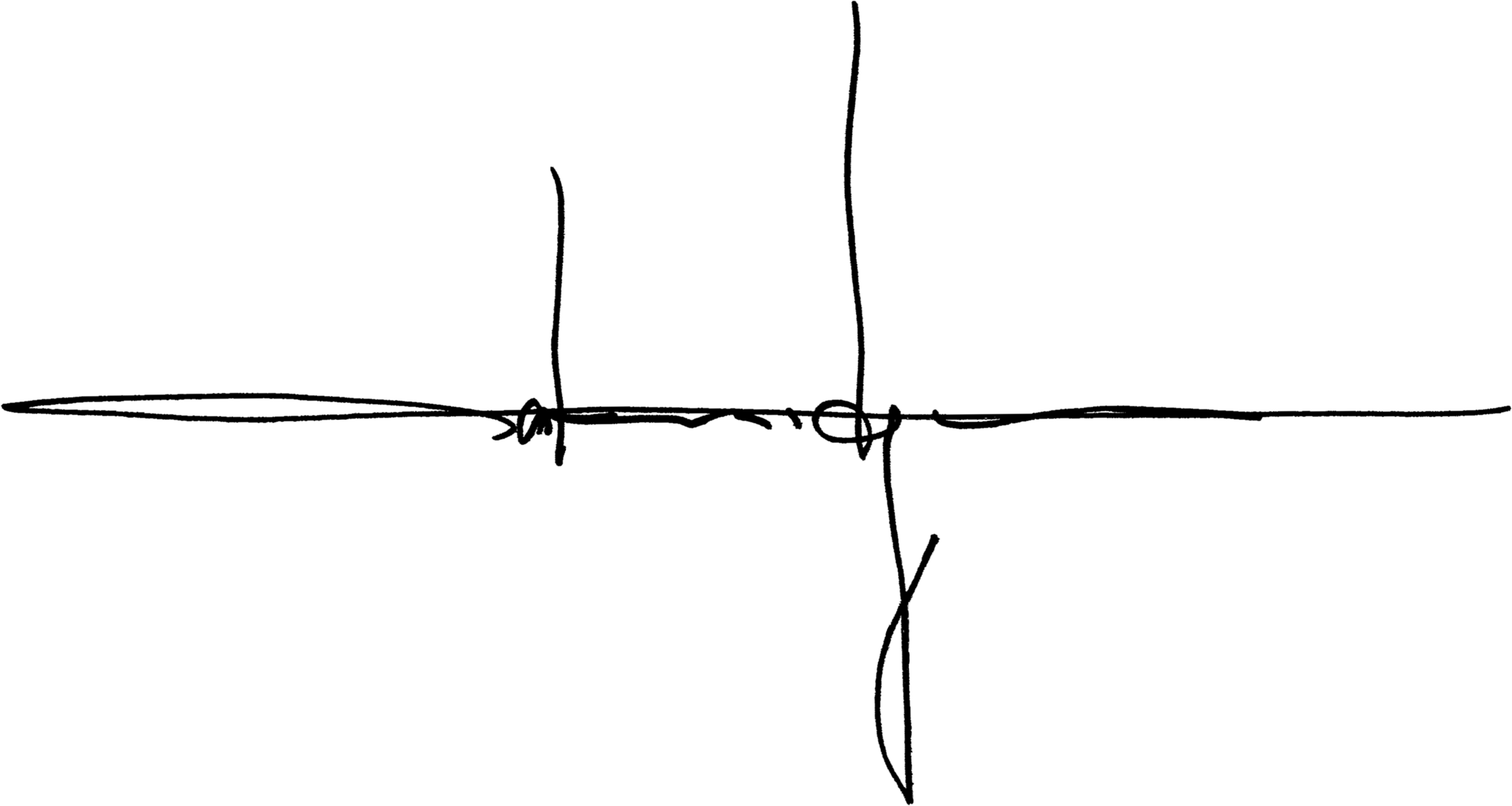萩原朔美さんは、最近原宿のアパートメントに引っ越してきました。
床は板張り、その中にポツンと置かれた白木の机の上には原稿用紙と先の研ぎ澄まされた鉛筆が10本ほど、少し離れたところにやはり白木のテーブルと、見るからに軽そうな籐の椅子が三つ、そして壁一面に取り付けられた本棚―折りたたんだ新聞も、読み終えた手紙も、鉢植えの花も、とにかく余分なものはどこにも見当たらないのです。「ねえ、セータや靴下や下着なんか、一体どこにしまってるの」
「写真とあ、古い手紙とか、新聞の切り抜きなど、たまったものはどうするの」
「それに一体どこでねるの」生活を感じさせるものは一切嫌いだと彼はいう。やかんもトースターも、そしてライポンFも、ほんとうはみんなしまっておきたいけど、使うたぶに出し入れするのもたまらないから、やむおえず外に出しておく。
冷蔵庫の上に洗いたてのブルーや白のタオルが積まれていた。黒に塗られた窓のブラインドと、バスルームのドアを除き、ほかはすべて白木。およそ色彩というものがない。
生命をはぐくむ子宮は、鮮やかなオレンジ色をしているのだろうか。萩原朔美の作品は、この無色の子宮のなかで、ある時は衝撃的に素早く、ある時はゆっくりと慎重に成長していくように私には思われる。―
『日本の個人映画作家3』 映像文化罪保護委員会 1976年