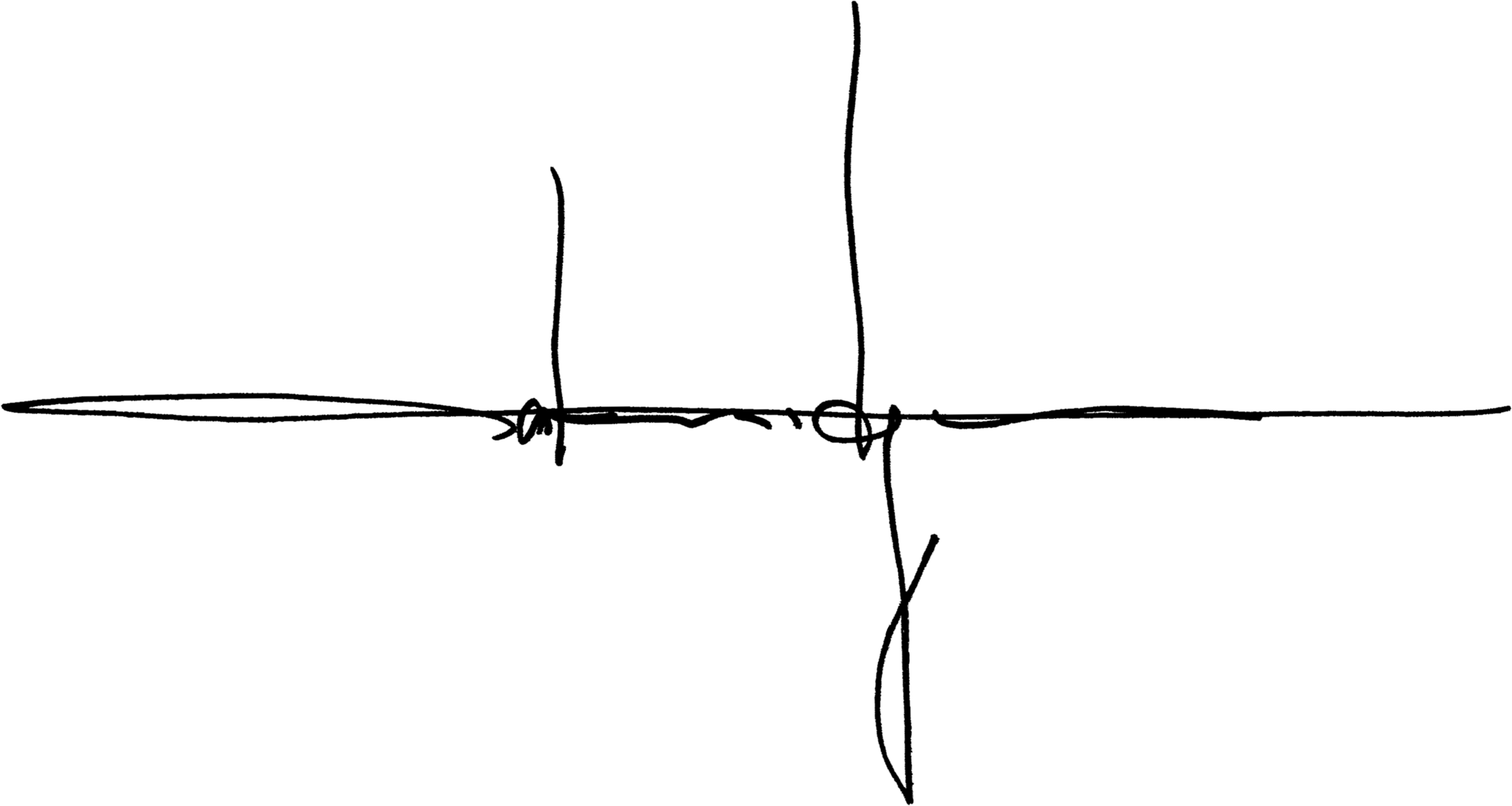彼のフィルムに『ストーン』というのがある。庭にある石を、ずっと記録したものである。ところが、フィルムの終りの方になって、石がふわりと舞い上がる。
石が舞い上がるからフィルムが終わったというのではないのである。石が庭からなくなるという現象は、われわれの日常の意識にはない。
しかし、石が空へ舞い上がるというのは、見えない世界に属する。石がどこかへ運びさられるというのも、リンゴが腐るのも、日常世界ではありえながら、考える必要のない事実である。
ただ、そういう事実が存在することを、人間は見ようとしない。合理的で機能的な世界にとって、そういう物の状態は考える必要がないからである。
萩原朔美は、おそらく石が空に舞い上がることを予想して、フィルムを作ったのだろう。リンゴが腐ることを予想したてリンゴの写真をとりつづけていたのだろう。
われわれの、何の疑いもなく続いている日常世界の記号的脈絡が、毎日同じように過ぎてゆくなかに、見ようとしないと見えない世界のあることを、彼はこれらの作品で示す。
それは、物の世界の終わりなのか。終わりのない世界の現象の一つなのか。何れかであろう。でも、おそらく萩原朔美にとっては、こうしてフィルムを作ったり、ビデオを撮ったり写真を版画にしたり、いろいろなメディアの中で、さまざまにイメージを置き換えてゆくことに、愉しみがあるらしい。
それは、<操作のユートピア>とでもいうべき世界であって、あのシャルル・フーリエのいう「蝶の原理」に近い。
フーリエは、一生涯とはいわなくても、一日の労働が、単一のものに縛られないで、ある仕事から別の仕事へ、蝶のように移りかわることが、人間の労働を活気づけることになると提案した。
萩原朔美も、同じように、物を一つの眼差しで縛りたくないのだろう。
記録の中におこる変化も、いくつかのメディアの中におこるイメージの変化も、すべては彼にとって、<操作のユートピア>に属することなのだ。
『日本の個人映画作家3』 映像文化罪保護委員会 1976年