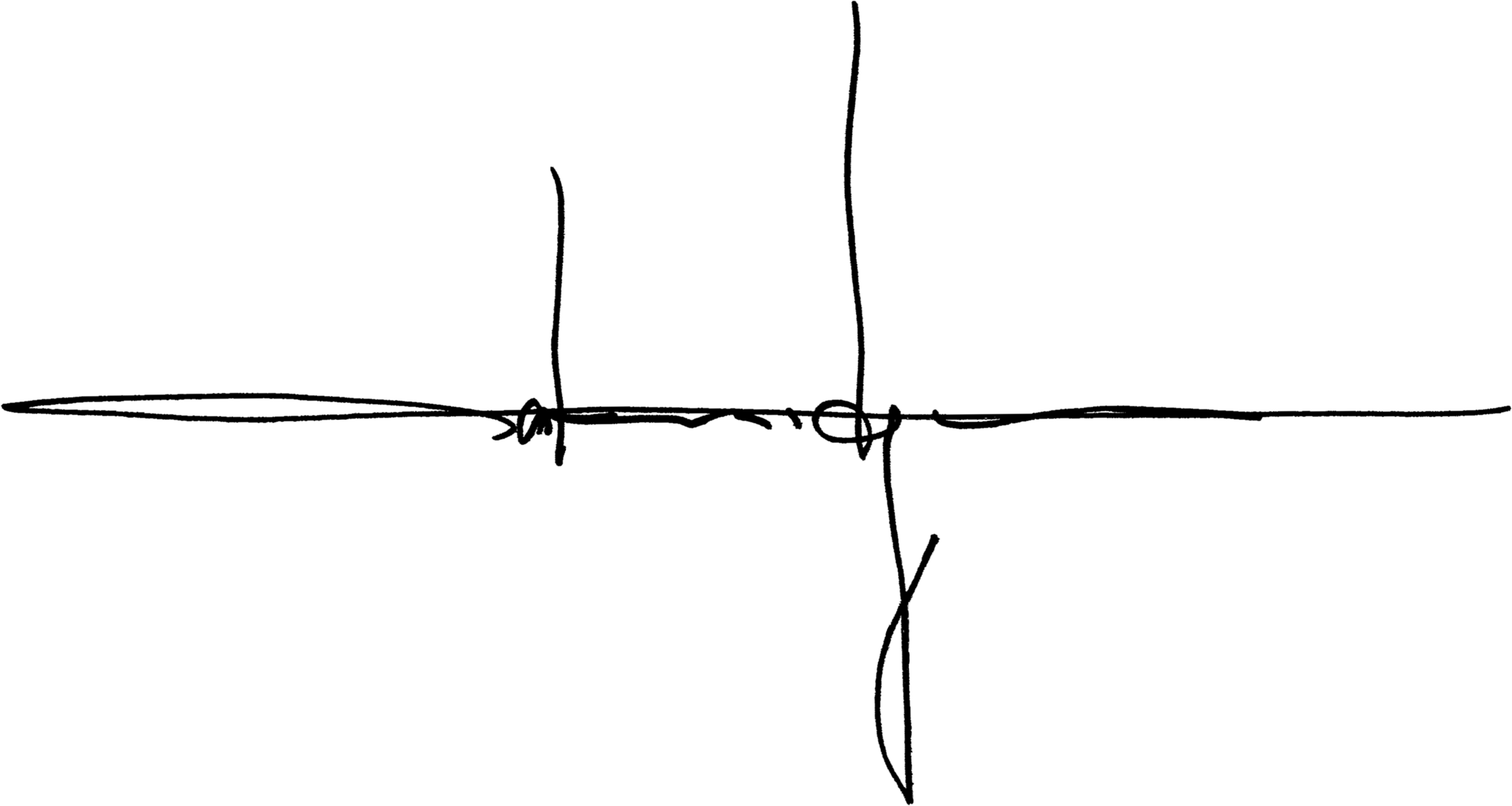萩原の試みているのは、メディウムとしての本と物体としての本の隙間に、遊びの仕掛けを挿入した産物である。もっとも、なかには「本を包む本」という都内の書店の包装紙を集めて製本した、萩原自身も認めるごとくいささか「ダジャレ」に堕した感のものもなくはないが、そうした作品だけというわけではない。
萩原の作品で目立つひとつの特徴は、今いった「遊びの仕掛け」として、本を見るもの、本のページをめくるものの行為に焦点を置いているということがある。
たとえば「透かす」は半透明の紙を綴じた本で、各ページに物体の名前が印刷してあって、その物体を紙を透かして見る、そしてその日付を記入するという指定がある。
「影の本」というのは、似た仕組みの本だが、ページの上に物体の影を映して見ることになっている。それに対して、物体としての本により傾斜している仕事もある。「木」は板に表紙をつけて本という体裁をとらせたものである。きわめて単純な構造だが、表紙に「木」という文字が刻印されているのがミソで、それは中味を「木」ということばのレベルで押さえようという表現である。何々の木というより具体的なレベルはここでは考慮されていないことに注目しなければなるまい。
本は印刷された紙を綴じたものである。それには不可避的に表紙と裏表紙がつく。それは本を自律な世界とするための二つの仕切りである。入り口と出口といってもいい。
美術家はこの二つの仕切りの中にいろいろなものを投げ入れる。すると「本」が生まれるのである。表紙と裏表紙という二つの仕切りは、絵画にとっての額縁と似ている。
美術家にとって表現のこうした仕切りというのは重要な意味をもつと思う。萩原の作品は、この本の仕切りというものを強く浮かび上がらせる。「本」のヴァラエティが多いほど「仕切り」がクローズアップされるのである。
『仕切りについて−萩原朔美の本−』 月刊美術評論 1979年9月号