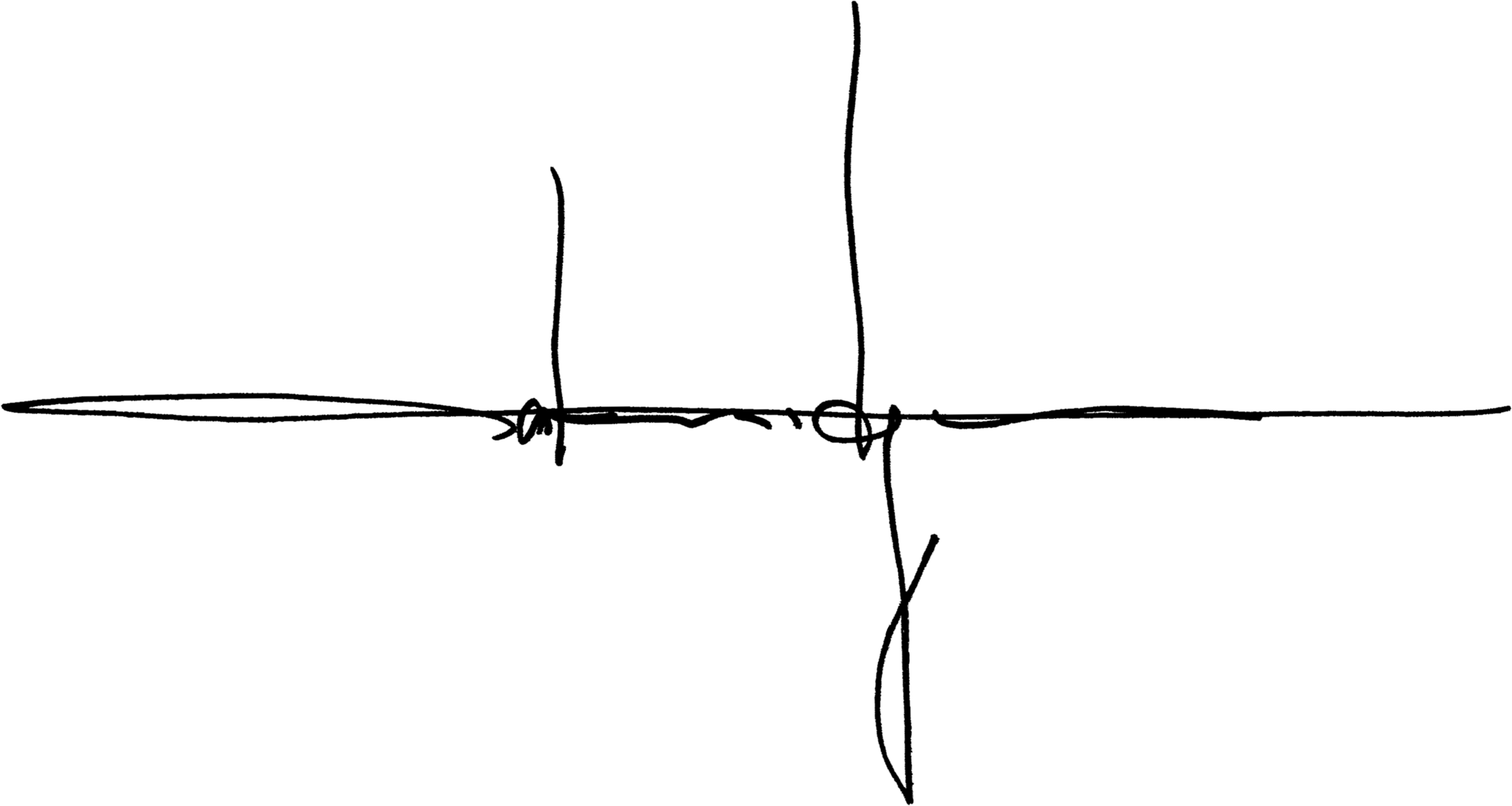・萩原朔美は自作の映画「少年探偵団」(未完)を天井桟敷の連中と途中まで作り、そのまま休団していた。
一九六七年「青森県のせむし男」の美少年役で俳優デビュー以来、演出までを手がけるようになっていたが、天井桟敷にいては自分の仕事ができないという憔悴感からの休団だった。結局それは永久の休団になってしまうのだが。休団を前後して、団員の松沢八百、安藤紘平、稲葉憲仁、それに渋川育由と私を誘って、「家族商会活動所」という映画作りのグループをでっち上げた。なにをやるわけでもなかったが、翌何には、写真家の山崎博を加えて、「FAMILY」という事務所を代官山もつことになる。これが月刊「ビックリハウス」の母体にもなっていく。
考えてみると、母一人子一人で育った萩原は、兄姉の多い私とは異なり、家族やグループといったものの幻想に執着するところがあった。
「悟空会」という空手のサークルを組織していたのもそうなのだろう。これは寺山修司にも共通するものだと思う。萩原はその頃、幻想の家族、幻想の会社、を組織して、漂泊の人のように揺らいでいた。・萩原朔美という人はある種の発想魔なのだ。しかし自分の手で作ろうとするマエストロ(職人頭)タイプではない。誰かにやらせて達成する。卵を産んでも自分では育てない鳥がいるが、そんな人なのだ。早速に、山崎博、安藤紘平、かわなかのぶひろ、『季刊フイルム』の編集をしていた高橋克己らが招集されて、企画書作りの会議が始まった。
・生活してみると、萩原が掃除好きであることがわかった。歌もよく口ずさんでいた。呑んだ帰り路には必ず鼻歌が出る。
なかでも一九七一年に日本歌謡大賞、日本レコード大賞の二冠に輝いた尾崎紀世彦の『また逢う日まで』(阿久悠作詞)はよく歌っていた。「二人でドアを閉めて、二人で名前消して」かどうかは知らないが、合意のうえで女房と別れた萩原も「別れのそのわけは、話したくない」のだろう。自己劇化、自己の客体化、自己の道化化。そしてその彼のうちに転がり込んだジゼールと私。
しかし三人にとっても、もうじき「また逢う日まで」である。この曲は、そののちも私たちのテーマソングになる。酔って家に帰った私たちは思いきり大声で、『また逢う日まで』を歌った。
『東京モンスターランド』 晶文社 2008年10月